
|
開会式
来賓祝辞
文部省生涯学習局長 草原克豪
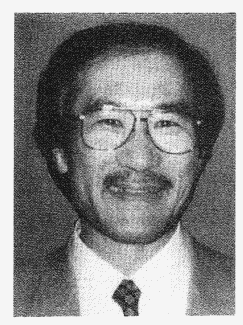
皆さん、おはようございます。
皆様方には日ごろから、それぞれの青年の家という施設の運営を通じて、青少年の教育に多大なご尽力をいただいております。この場を借りて、改めてお礼を申し上げたいと思います。
ご承知のように、青少年の教育をめぐっては合いろいろな問題が提起されております。文部省に中央教育審議会というのがございまして、この審議会においても、「21世紀を展望した今後の教育のあり方」ということについて、現在審議を重ねているところでございます。この夏には答申をまとめるということを目標にしまして、大変熱心な議論がなされているところでございまして、時々その様子が新聞などにも報道されますので、皆さんもごらんになっておられると思います。この議論の中で今強調されているのが、「生きる力」と「ゆとり」ということなんですね。これは青少年教育、特に青年の家のような学校外の教育を担当する立場として、大変考えさせられることだと思います。
こういう生涯学習の時代になりますと、一生を通じて学び続けるということが大事なんですけれども、しかし、一生を通じてといっても、年をとってから急に何かを始めようと思ってもなかなか難しいわけであります。やはり若い頃から何かに関心を持って取り組む、そういう習慣、姿勢を養っておく必要があるんですね。もっと言えば、もっと小さい頃から、幼少の頃からそういう学習が大事なわけでありまして、そういう観点から見ると、学校教育ではそういうふうにして一生学び続けることが大事だということを学ぶこと、それから、自分で考えて、自分で判断をして、自分で行動する、そういう力を養うことが本来、一番大事なことのはずなんです。
そのはずなんですが、実際はなかなかそうはいかないという問題がありまして、どうしても学校では知識の一方的な教え込み、あるいは詰め込みに傾いていってしまうわけですね。そして、上級学校に入るために準備をするのが、あたかも学校教育の正常な姿であるかのようになってしまいます。ここに大きな問題があると思うんです。学校自身がもっと子供たちの、長い目で見た成長を助けるような教育をする必要があると思っております。
しかしこれは、学校だけで解決できることではない。むしろ問題は、子供たちの生活の中で、学校が占める時間が圧倒的に大きくなっているというところにあると思うんですね。学校の外で、自分自身でいろいろな体験をしながら学んでいく、そういう過程が大事だと思うんです。
中教審で言っております「ゆとり」というのもそういうことなんですね。「生きる力」というのも、そういういろんな体験を通じて養うことができる、こういう考え方に立っていると思うのです。そのためには学校外の活動が大事です。学校外の活動の時間を確保するために、学校週5日制ということを、今、月に2回実施しているわけです。学校外の活動にもいろいろな場があり、いろいろな活動内容があると思いますけれども、その中で重要な役割を果たしているのが皆様方の青年の家であろうかと思います。
この青年の家のあり方については、昨年7月、文部省に置かれました青年の家のあり方についての調査研究協力者会議の報告が出ております。皆様方に
前ページ 目次へ 次ページ
|

|